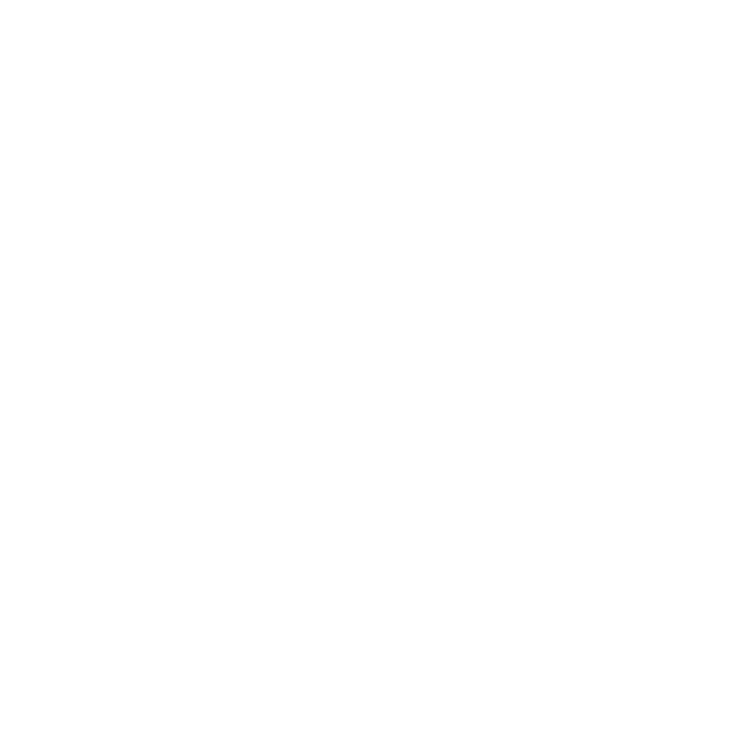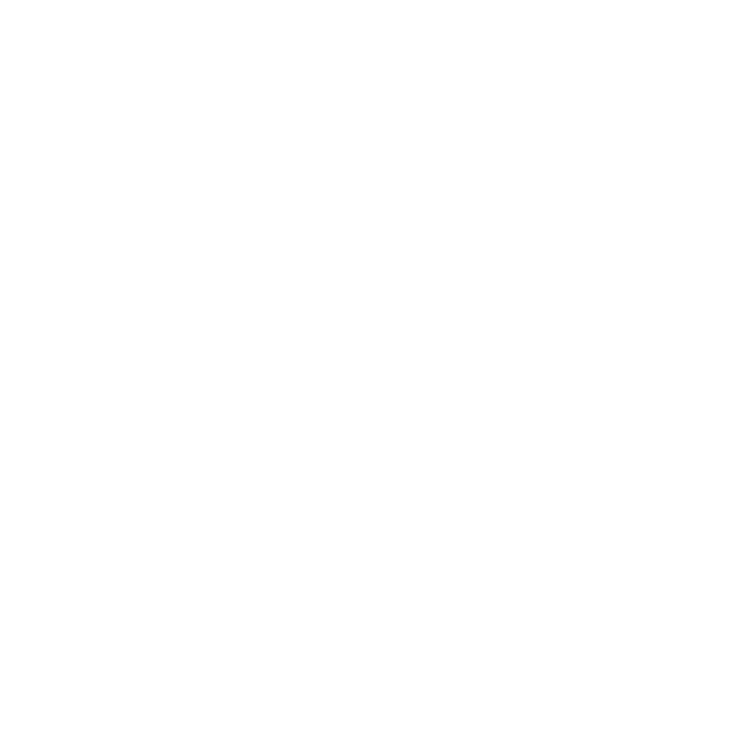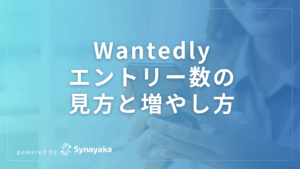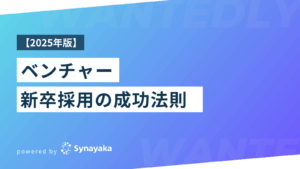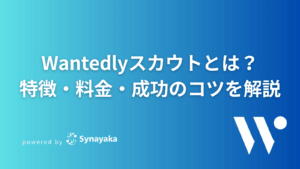応援数で表示順位が変わる?Wantedly応援機能の仕組みと攻略法
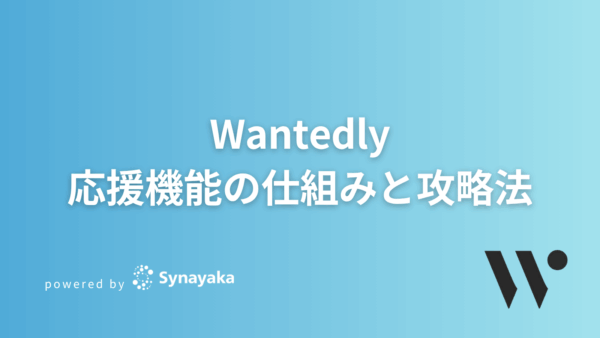
近年、Wantedlyの「応援」機能が採用成果に直結する要素として注目されています。
特に共感を重視するWantedlyでは、この「応援数」が表示順位や応募率を左右する重要なシグナルになっています。
一方で、「応援って何?」「誰にどうやって頼めばいいの?」と、うまく活用できていない企業も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、Wantedlyの応援機能の仕組みから、表示順位との関係、応援数を増やす実践テクニックまで、徹底的に解説します。
こんな方におすすめ
- 応援機能の意味や効果がわからない
- 表示順位を上げてPV・応募数を増やしたい
- 応援される求人・ストーリーの作り方を知りたい
本記事を読めば、「応援」からはじまるWantedlyの成果最大化の設計図が一気に理解できます。
Wantedlyの応援機能とは?|仕組みと目的を正しく理解する

応援機能の概要|“いいね”とは違う「共感の証」
Wantedlyの「応援」機能は、求人やストーリーに対してユーザーがワンクリックでリアクションできる機能です。
一見SNSの「いいね」に近い印象を受けるかもしれませんが、単なる好意の表明ではなく、“この会社・この求人を応援したい”という共感や期待のシグナルとして扱われています。
特にWantedlyは「共感採用」を軸に設計されたプラットフォーム。応援数はその“共感の可視化”とも言え、企業にとっては自社の魅力がどれだけ伝わっているかのひとつの指標になります。
どこに表示される?|求人・ストーリー・フィード上での見え方
応援ボタンは、主に以下の場所でユーザーがクリック可能です。
- 求人ページの上部(職種タイトルの下)
- ストーリー記事の冒頭・文末
- タイムライン(フィード)上のカード型表示部分
応援されると、その投稿には「●●さん含む○人が応援しています」という表示がつき、信頼感や話題性を後押しする効果があります。
特にフィード上では、応援数の多い投稿ほど「人気順」での表示が上がりやすくなるため、応援される=露出が増えるという構造です。
なぜ導入された?|Wantedlyの“共感採用”思想と応援の関係
Wantedlyは、「給与や条件ではなく、“共感”で人と会社をつなぐ」ことをコンセプトとしています。
その文脈で導入されたのが、この「応援」機能です。単なる情報のやりとりではなく、共感を媒介にしたエンゲージメント(関係性)を可視化し、拡張するための設計が背景にあります。
たとえば、「こんな価値観の会社、応援したい」「この挑戦、おもしろそう」といった感情が1クリックで表現できるようになることで、企業側の熱量やメッセージが伝わりやすくなります。
応援数が表示順位に与える影響|アルゴリズムの仕組みとスコア設計

新着順・人気順・おすすめ順の違い
Wantedlyでは、求人やストーリーの表示順に大きく3つの分類があります。
- 新着順:公開された日時が最新の順に表示
- 人気順:PV数・応援数・シェア数などの反応率が高い順に表示
- おすすめ順:ユーザーの属性や行動履歴に基づくAIレコメンド
このうち「人気順」「おすすめ順」は応援数の影響を強く受ける順位軸です。新着順は時間とともに埋もれていきますが、応援されることで表示順位を押し上げる再浮上のチャンスが生まれるのです。
応援数が与える表示順位スコアへの影響とは?
Wantedlyのアルゴリズムは非公開ですが、経験的に以下のような構造が見えてきます。
- 応援数が多い投稿は「人気順」で上位に表示されやすい
- 応援数×クリック率の高さが「おすすめ順」にも影響する
- 短時間に集中して応援が集まると、AIが“注目投稿”と判断する傾向がある
つまり、応援は単体ではなく「表示→応援→さらなる表示」という正のスパイラルを作る“起点”になります。
このスコア構造を理解せずに運用すると、せっかく良い求人やストーリーを書いても、誰の目にも触れずに埋もれてしまうことになります。
応援数だけでは不十分?|他の指標(PV、クリック率等)との相関
もちろん応援数が多ければ表示されやすくなりますが、それだけで十分ではありません。表示順位に影響するその他の要素には以下も含まれます。
- PV数(閲覧数)
- CTR(クリック率)
- エンゲージメント率(応援/PV)
- タグの一致率(職種・業種)
- 投稿の更新頻度・新しさ
応援数を“どのような反応率で得ているか”が評価されており、見せ方・届け方の設計次第で同じ応援数でも結果が変わるのが現実です。
つまり、ただお願いして応援をもらうのではなく、「応援されやすい構造」を作ることが重要だということ
応援を増やす3つの方法|チーム・SNS・設計で“共感の輪”を広げる
まずは社内から|応援文化を定着させる仕組み
Wantedlyの応援数を安定的に伸ばすには、まず社内のメンバーを巻き込むことが鉄則です。特に新着投稿が公開された直後の「初動応援」が重要で、早期に一定数のリアクションがつくことで人気順・おすすめ順への掲載可能性が高まります。
効果的なのは次のような社内仕組みづくりです:
- Slackなどで「応援依頼チャンネル」を作る
- 社内でローテーション制を導入(週替わりでリーダーを設定)
- 「応援→シェア→コメント」までがセットと伝える
応援依頼を「お願いベース」にせず、「会社を一緒に育てる文化」として定着させることが重要です。
SNSとの連動|シェア→リアクションを最大化する導線づくり
社内だけでなく、社外の共感を得る“発信設計”も応援数を左右します。
その中でもSNS(特にX/Twitter・LinkedIn)は、拡散と応援の導線をつなげやすい重要なチャネルです。
投稿時には以下を意識しましょう:
- 応援リンク付きの投稿を発信(例:「この求人、応援してもらえると嬉しいです!」)
- ストーリーや求人に「シェアしたくなるコピー」を入れる
- 共感されやすい内容(苦労・挑戦・展望)を強調
SNS上の拡散は、新しい応援者=共感候補との接点創出でもあります。応援を通じた認知拡大とスコア上昇の“二兎”を狙いましょう。
タイトルと画像が9割?|“応援されやすい”設計の型
応援数を増やすためには、「読んでみたくなる→共感したくなる」投稿を設計する必要があります。
その鍵を握るのが、タイトルとメイン画像の設計です。
- タイトルは「読み手視点」+「感情を動かす言葉」で構成
例:「事業が止まった1年間。それでも挑戦を続けた理由」 - 画像は“リアルさ”や“ストーリー性”がある写真を使用
例:オフィスの様子/働くメンバーの自然な表情/手書きのビジョンボードなど
これはまさに、「応援したくなる世界観の構築」です。
ただ記事を書くのではなく、「応援を呼び込むための舞台づくり」を意識することで、数字は確実に変わります。
応援される求人・ストーリーの特徴とは?|共感が可視化される構造設計
「らしさ」がある会社は強い|EVPとペルソナが応援数を変える
Wantedlyで応援される会社には、ある共通点があります。それは、「自社らしさ」が明確に言語化されていること。
これは、採用におけるEVP(Employee Value Proposition:従業員にとっての価値)と、ペルソナ設計の精度によって左右されます。
応援されない投稿の多くは、「誰に向けて、何を伝えたいのか」が曖昧です。逆に、候補者の視点に立ち、“自分ごと化”できる発信ができていると、自然と応援したくなる心理が働きます。
- 「なんとなく良さそう」ではなく「この会社、自分に合いそう」と思わせる
- 抽象ワードでなく、感情や行動が具体的に想起できる表現を使う
共感を呼ぶ設計とは、ターゲットが“共鳴するメッセージ”を届けることなのです。
3つの共感パターン|ビジョン/人・カルチャー/戦略型
応援されやすいストーリーや求人には、大きく3つの共感パターンがあります。
- ビジョン型:「何のために存在しているか」
例:「10年後、当たり前になる未来を私たちが先につくる」 - 人・カルチャー型:「誰と、どんな価値観で働くか」
例:「家族よりも長く一緒にいる“仲間”と、笑って挑戦したい」 - 戦略・成長型:「どう戦って、どこへ向かうか」
例:「1人で始めた事業が1年で100社導入。“逆張り”で市場を切り開く」
これらの型を活用すれば、応援の起点になる“共感ストーリー”を仕立てやすくなります。型にはめて考えることで、誰でも伝え方の解像度が上がります。
応援されない投稿の特徴|情報の羅列と“刺さらなさ”
逆に、応援されない投稿には、以下のような特徴があります。
- 会社概要や事業説明ばかりで“意味”が伝わらない
- 誰に向けたメッセージか不明瞭(=全方位にぼやけている)
- ストーリーが“情報の報告”で終わっている(背景・葛藤・未来がない)
応援されるには、「この会社、応援したくなる」と読み手の心が動く要素が必要です。
つまり、「構造(ペルソナ・EVP)」「表現(ストーリー)」「見せ方(タイトル・画像)」の3点を揃えて、“共感の舞台”を整えることが鍵なのです。
応援機能を活かす運用設計|“見られる→刺さる”Wantedly改善アクション
応援→表示→応募の導線を仕組み化する
応援は「なんとなくもらうもの」ではなく、採用成果につなげるための導線設計の一部です。
PVを増やし、順位を押し上げ、エントリーにつなげるには、以下の流れを仕組み化する必要があります。
- 投稿直後に社内で応援→初動ブースト
- 応援された投稿がタイムライン上で表示上昇
- 表示回数が増えることでクリック・閲覧が拡大
- 内容に共感した候補者が応募やフォローを実行
この流れを毎回狙って再現できるようにすることで、「継続的に成果が出るWantedly運用」が実現します。
数値で振り返る|KPIに組み込むべき応援・PV・CTRの指標
成果につなげるためには、感覚ではなく数字で振り返ることが重要です。
特に以下の指標をKPIに設定すると、改善の仮説が立てやすくなります。
- 応援数(初動24時間以内)
- PV数(1週間単位で推移を観察)
- CTR(タイムライン表示数に対するクリック率)
- 応援率(PVに対する応援数)
例:
「求人タイトルを変更したらCTRが3.2%→4.6%に改善」「ストーリーに苦労話を加えたら応援率が倍増」など、改善サイクルを数字で回せば再現性のある施策蓄積が可能になります。
第三者視点を活用する|“応援されるか”を見抜く改善プロセス
最後に欠かせないのが、“主観の罠”を回避する視点です。
企業自身が「良い投稿を書いた」と思っていても、外から見れば刺さっていないケースは多々あります。
そのため、以下のような第三者視点の導入が効果的です。
- 社外の仲間や採用支援パートナーにフィードバックをもらう
- ストーリーや求人の“共感力”をテスト的に共有・観察する
- 過去に応援数が多かった投稿と比較する
Synayakaでは、実際のWantedlyページを一緒に見ながら「どこをどう直すと応援が増えるか」を構造・視覚・言語の三方向からフィードバックしています。
一人で悩まず、第三者視点をうまく活用することが、次の一手につながります。