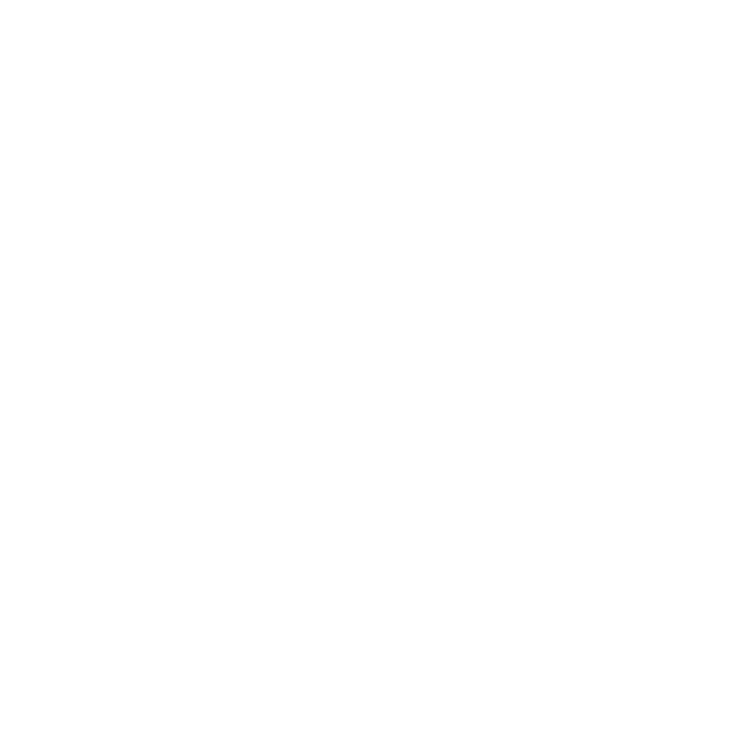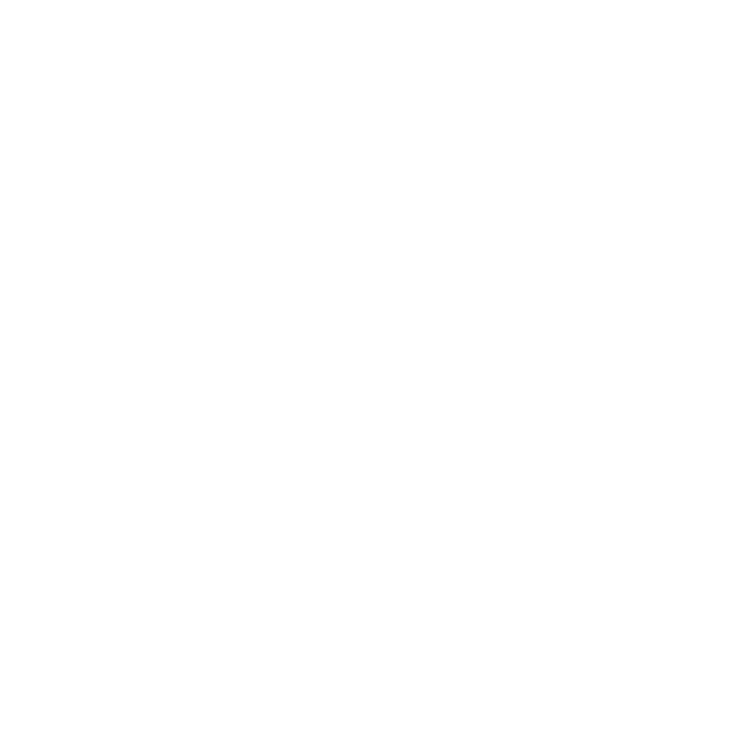RPOとは?BPOとの違い・採用効果・市場規模まで徹底解説【2025年版】

採用業務を外部に委託する「RPO(Recruitment Process Outsourcing)」に近年注目が集まっています。
人手不足で採用難が続くなかで、自社だけで採用を完結させることに限界を感じている方も多いのではないでしょうか。
特にスタートアップや中小企業では「採用の母集団形成がうまくいかない」「採用担当者が不足している」といった課題を抱えるケースが増えています。
本記事では、RPOとは何か、BPOとの違い、導入のメリット・デメリット、市場規模や最新動向、そして具体的な成功事例 までをわかりやすく解説します。
1. RPOとは?意味と仕組みをわかりやすく解説

1. RPO(Recruitment Process Outsourcing)の定義
RPOとは「Recruitment Process Outsourcing」の略であり、企業が自社の採用業務の一部または全部を、外部の専門会社に委託する仕組みのことを指します。
従来の「採用代行」と似ていますが、単純な作業代行ではなく、戦略立案から採用チャネル選定・母集団形成・選考フロー改善・内定者フォローまで包括的に担う 点が特徴です。
2. 採用代行との違いと位置づけ
「RPO」とよく混同されるのが「採用代行(業務代行型のアウトソーシング)」です。
採用代行は、求人掲載や面接日程調整など、限定的な作業を切り出して依頼することが多いですが、RPOは採用の成果責任を前提に、プロセス全体を改善・運用する 点で異なります。
そのため、採用代行が「オペレーション寄り」なのに対し、RPOは「戦略とオペレーションの両輪」を担う存在と言えます。
3. RPOが注目される背景
RPOが注目される理由は大きく3つあります。
- 採用難の加速:労働人口の減少と求人倍率の上昇により、母集団形成が困難に。
- 人事リソース不足:特に中小企業やスタートアップでは、専任人事がいないケースも多い。
- 採用の専門性の高度化:求人媒体の多様化、ダイレクトリクルーティングやSNS採用など、新たな知識と運用ノウハウが求められる。
これらの背景から、RPOは「人事の工数を補完する存在」ではなく、企業の採用力を強化する戦略的パートナー として導入が進んでいます。
2. RPOとBPOの違い|採用領域に特化したアウトソーシング

1. BPO(Business Process Outsourcing)の範囲
BPOとは「Business Process Outsourcing」の略で、企業が自社の業務プロセス全般を外部に委託する仕組みを指します。
対象は人事だけでなく、経理・総務・カスタマーサポート・IT運用など幅広く、間接業務の効率化やコスト削減 を目的に導入されることが一般的です。
BPOは「広範な業務領域の外注」という点が特徴であり、バックオフィス機能を中心に使われてきました。
2. RPOがBPOと異なるポイント
一方でRPOは、BPOの中でも「採用領域」に特化したアウトソーシング形態です。
具体的な違いをまとめると以下の通りです。
- 対象範囲:BPO=経理・総務・ITなど多岐にわたる/RPO=採用業務に限定
- 目的:BPO=コスト削減・効率化が中心/RPO=採用成果の最大化(応募数・質・定着率)
- 関与度:BPO=業務処理中心/RPO=戦略立案から実行まで伴走
つまりRPOは単なる業務委託ではなく、企業の採用成功に直結する専門領域型アウトソーシング なのです。
3. 図解でわかるRPOとBPOの比較
イメージを持ちやすくするために、RPOとBPOを整理すると以下のようになります。
【BPO】広い業務領域の外注
人事/経理/総務/CS/IT運用 … など全般
【RPO】採用領域に特化した外注
求人設計/スカウト代行/面接調整/内定フォロー … 採用成果に直結このようにBPOは「業務効率化のパートナー」であるのに対し、RPOは「採用成果のパートナー」と位置づけられます。
採用が経営課題となっている現代において、RPOの需要が高まっているのはこの違いによるものです。
3. RPO導入のメリットとデメリット|採用効果の全体像

1. RPOを導入するメリット(質・量・効率)
RPOを導入する最大のメリットは、採用成果の最大化 に直結する点です。主な効果は以下の通りです。
- 応募数の増加:複数チャネルを活用し、母集団形成を強化
- 候補者の質向上:ペルソナ設計や訴求改善により、定着率の高い人材にリーチ
- 採用スピードの短縮:専門チームが運用することで、選考リードタイムを圧縮
- 工数削減:求人票作成やスカウト送信、面接調整などの事務作業をアウトソース
- ノウハウの獲得:専門家の知見を取り込み、自社の採用力を底上げできる
特にスタートアップや成長企業では、限られたリソースを事業成長に集中させつつ、採用成果を確保できる点が大きな魅力です。
2. デメリット・注意点(コスト・ノウハウ依存など)
一方で、RPOには注意すべき点もあります。
- コストが発生する:月額数十万円〜数百万円の固定費や、成果報酬がかかる場合もある
- 自社ノウハウの蓄積不足:丸投げ型にすると、自社に知見が残らず依存状態になるリスク
- ベンダー選定の難しさ:提供範囲や強みが会社ごとに異なるため、ミスマッチが起きやすい
- カルチャーマッチのずれ:外部委託ゆえに、自社文化を正しく伝えきれない場合もある
これらのリスクを避けるためには、「何を任せて何を内製するか」の切り分けが重要になります。
3. 内製化との比較から見えるRPOの効果
RPOと内製化を比較すると、次のような整理ができます。
- 内製化:コストは抑えやすいが、工数が膨大で専門性不足になりがち
- RPO:コストはかかるが、成果・スピード・ノウハウの点で優位性がある
特に「短期間で採用成果を出したい」「専門人材の採用に強化したい」といったケースでは、内製よりもRPOの方が高い費用対効果を発揮します。
逆に「採用規模が小さい」「自社でじっくり採用力を育てたい」場合は、部分委託やスポット活用が適しています。
4. RPOの市場規模と国内外の動向
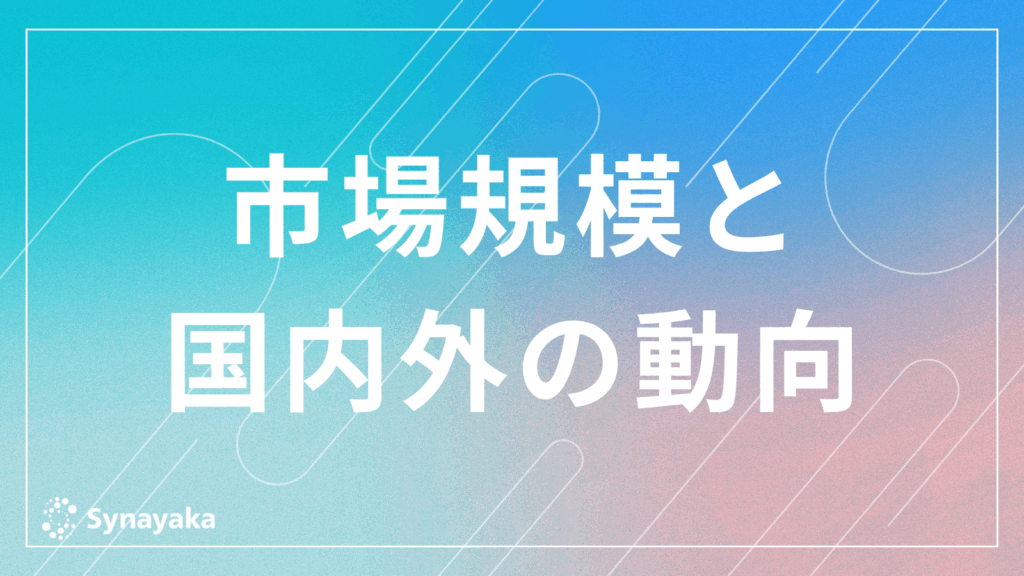
1. 国内RPO市場の成長と規模感
近年、日本国内のRPO市場は拡大を続けています。
背景には以下の要因があります。
- 慢性的な採用難:有効求人倍率は直近数年で高止まりし、特にIT・建設・医療などで人材不足が深刻化。
- 採用の複雑化:求人媒体・SNS・スカウトなどチャネルが多様化し、専門知識が不可欠に。
- 人事リソース不足:中小・ベンチャー企業では専任人事が不在のケースが多く、外部委託ニーズが増加。
矢野経済研究所などの調査によれば、国内RPO市場は2020年以降右肩上がりで成長しており、2025年には約1,000億円規模に到達する と予測されています。
これは単なる「人事業務の外注」から、「採用成功を伴走する戦略パートナー」としてRPOの位置づけが高まっていることを示しています。
2. 海外におけるRPO導入のトレンド
海外、とくに欧米では、RPOはすでに一般的な採用手法となっています。
- 北米:大手企業では「グローバル採用の一括委託」としてRPOを利用するケースが多い。
- 欧州:多国籍企業での標準的な採用モデル。多様な言語・文化に対応するため、現地RPOベンダーとの連携が進む。
- アジア:新興国市場でも外資系企業を中心に導入が拡大しつつあり、特にIT・製造業でニーズが高まっている。
海外のRPO市場は数兆円規模とも言われ、「採用を内製せず、外部パートナーと共に最適化する」 という考え方が浸透しています。
3. 今後の成長予測と企業が押さえるべき視点
今後、日本におけるRPO市場もさらに成長すると見込まれています。
その理由は以下の通りです。
- DX・AI活用の加速:ATS(採用管理システム)やAIスカウトの普及により、RPOベンダーが提供できる付加価値が増加。
- 採用の戦略化:単なる代行ではなく、EVP設計や採用ブランディングまで踏み込むRPOが主流に。
- 中小企業への浸透:従来は大手中心だったが、スタートアップや地方企業にも利用が広がる。
企業が押さえるべき視点は、「自社に必要なのはどの範囲のRPOか」 という点です。
フルアウトソース型か、部分委託型かを見極めることで、無駄のない投資につながります。
5. RPOのサービス範囲と対応領域

1. 母集団形成(求人広告・スカウト・ダイレクトリクルーティング)
RPOの代表的な役割は「母集団形成」の支援です。
求人広告の出稿設計から原稿作成、各種媒体の運用、さらにはダイレクトリクルーティングのスカウト代行までを担います。
特に近年は、Wantedly・LinkedIn・BizReach などの運用型媒体を活用し、アルゴリズムや反応率の改善を重ねながら応募数を最大化する支援が増えています。
2. 選考プロセスの支援(書類選考・面接調整・同席)
母集団形成だけでなく、選考プロセス全体を支援できるのもRPOの特徴です。
- 書類選考の一次フィルタリング
- 面接候補者への連絡・日程調整
- 必要に応じた面接同席・フィードバック設計
これにより、人事担当者は「最終判断」や「候補者との関係構築」といったコア業務に集中できるようになります。
3. 内定フォロー・候補者体験設計までのサポート
RPOのサービスは、内定出し以降のフェーズにも及びます。
- 内定承諾率を高めるためのクロージングフォロー
- 入社までのオンボーディング設計
- 候補者体験(Candidate Experience)の改善施策
特に売り手市場では「内定辞退」が大きな課題となるため、RPOが候補者とのコミュニケーションを強化し、入社までつなげる役割 を果たします。
6. RPOの費用相場と契約形態
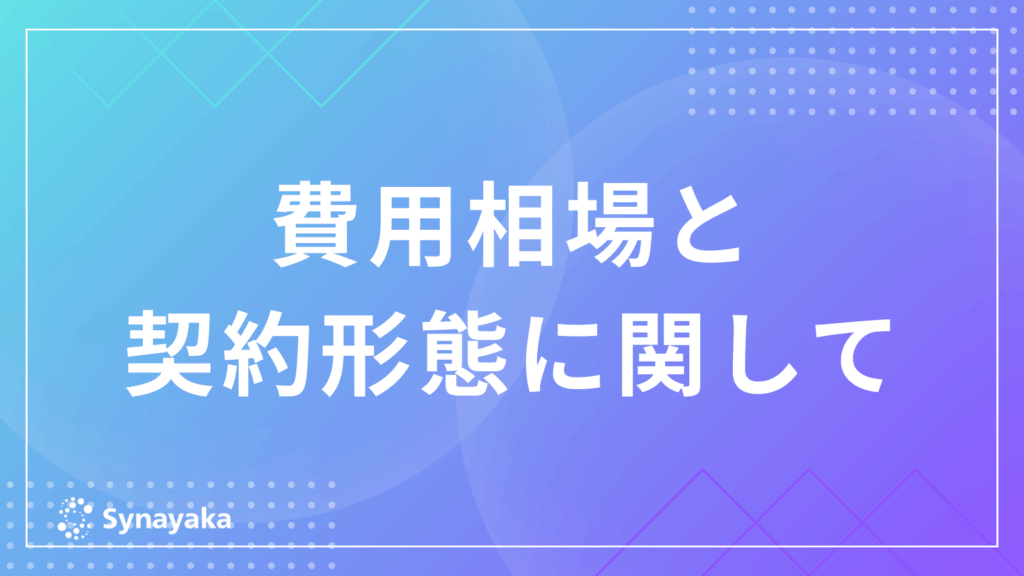
1. 月額固定型の料金相場
RPOの基本的な契約形態の一つが「月額固定型」です。
これは「採用の一定範囲をまとめて委託」する形式で、相場は 月額30万〜100万円前後です。
委託範囲に応じて変動し、スカウト送信や面接調整まで含めると高めになる傾向があります。
特徴はコストが安定するため、継続的な採用運用や仕組みづくりに向いている 点です。
2. 成果報酬型・従量課金型の特徴
月額固定型の料金相場が多い一方で、「成果報酬型」「従量課金型」という契約方式もあります。
- 成果報酬型:採用が決定した場合にのみ費用が発生するモデル。人材紹介に近い仕組みで、年収の20〜35%が手数料となるのが一般的。短期で採用成果を出したい場合に向いています。
- 従量課金型:スカウト送信数や選考代行件数ごとに課金する方式。1通あたり数百円〜数千円、面接調整1件あたり数千円など、スポットで必要な分だけ依頼できる のが特徴です。
これらは固定費を抑えられる一方、成果が出るまでの総額は高くなるケースもあります。
3. 契約期間・SLAにおける注意点
RPOを契約する際に注意すべきポイントが 契約期間とSLA(サービス品質保証) です。
- 契約期間:通常は3ヶ月〜6ヶ月が多い。短期すぎると成果が出にくく、長期すぎると柔軟性が失われるため、まずは半年程度から始めるのが一般的。
- SLA(サービス品質保証):例えば「スカウト送信数」「求人改善の頻度」「レポーティング項目」などを明確に定義しておくことで、期待値のズレを防げます。
費用だけでなく、どこまでの成果をコミットしてもらえるか を確認することが、RPO活用の成否を分けるポイントとなります。
7. RPOを活用すべき企業の特徴|向いているケースと注意点
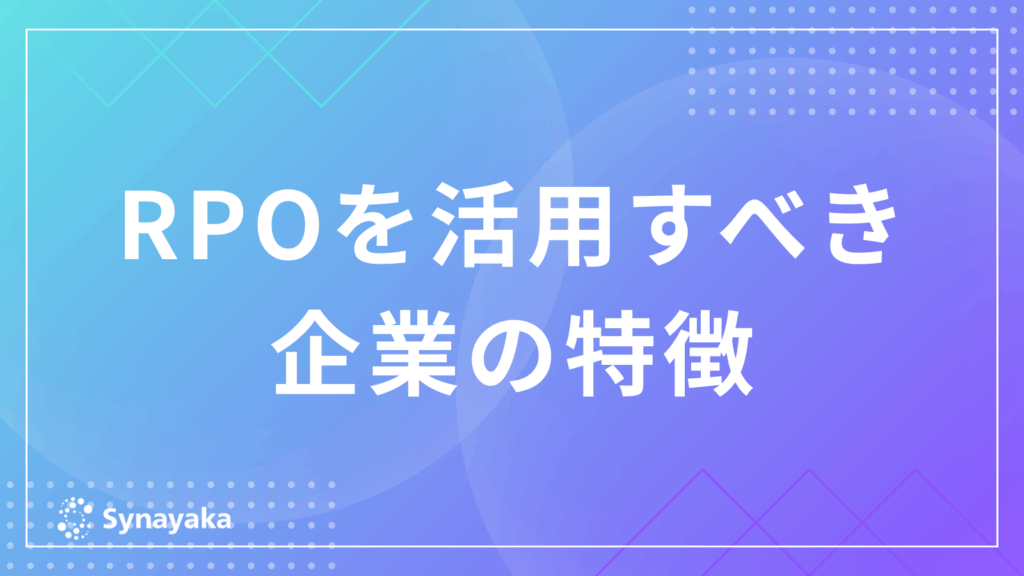
1. 新卒・中途・大量採用での活用シーン
RPOは、特に採用数が多い場面で効果を発揮します。
- 新卒採用:説明会運営やエントリー管理、面接調整など膨大な工数を削減できる
- 中途採用:スカウトや求人票ブラッシュアップを通じて、質の高い母集団形成を実現
- 大量採用:飲食・小売・コールセンターなど、短期間で多人数を採用するケースで有効
こうした採用ボリュームの大きい業態では、RPOを導入することで人事部門の負担を大幅に軽減できます。
2. スタートアップや成長企業における有効性
スタートアップや急成長中の企業は、人事専任者がいなかったり、採用ノウハウが社内に蓄積されていなかったりするケースが多くあります。
RPOを導入することで、
- 採用の戦略設計から運用まで一気通貫でカバー
- 採用広報やEVP設計などブランディング面も支援
- 限られたリソースを事業成長に集中できる
というようなメリットが得られます。
特に「初めての採用体制づくり」や「採用数が急増するタイミング」では、RPOが心強いパートナーになります。
3. RPO導入が不向きなケース(避けるべき状況)
一方で、RPOが必ずしも適していないケースもあります。
- 採用計画が小規模すぎる:年間数名レベルならコストに見合わない場合がある
- 採用要件が特殊すぎる:ニッチ領域や高度専門職は、RPOよりヘッドハンティングが有効な場合も
- 社内にノウハウを蓄積したい:長期的に「内製化」を重視するなら、外部依存はリスクになる
こうした状況では、部分委託(スポット支援)やコンサルティング活用 のほうが適している可能性があります。
✅ ポイントまとめ
RPOは「規模が大きい採用」「リソース不足の企業」「採用をスピーディに仕組み化したい企業」に向いています。
逆に「小規模採用」「特殊職種のみ」では慎重に検討する必要があります。
8. RPOサービスの選び方とチェックリスト
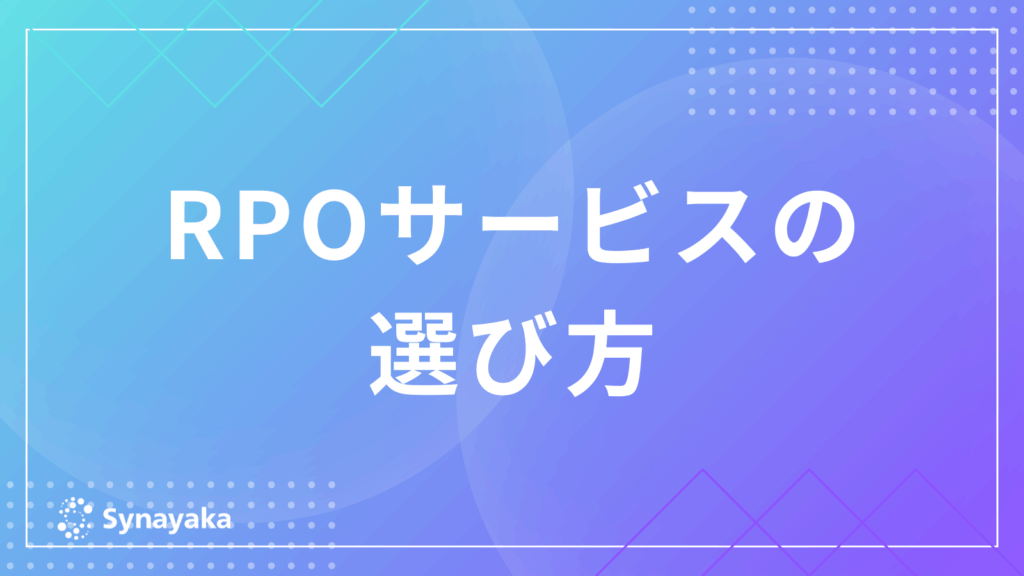
1. ベンダー選定で重視すべきポイント
RPOを導入する際に最も重要なのは、適切なベンダー選びです。
比較すべきポイントは以下の通りです。
- 得意領域:新卒採用/中途採用/ハイクラス/大量採用など、強みはベンダーごとに異なる
- 支援範囲:求人作成のみか、スカウト代行、面接調整、内定フォローまで対応するか
- ノウハウの深さ:媒体運用・アルゴリズム理解・ブランディング支援などの実績
- レポーティング精度:KPI設計や改善提案があるか
これらを比較することで、自社の採用課題にマッチするパートナーを選定できます。
2. 実績・ノウハウ・体制の比較方法
信頼できるベンダーかどうかを見極めるためには、実績と体制の確認 が欠かせません。
- 導入実績:同業界や同規模企業での支援経験があるか
- ノウハウの公開:セミナー・ホワイトペーパー・事例紹介の有無
- 担当体制:専任コンサルタント制か、複数担当か、オンサイト対応が可能か
特に「人事担当者のように伴走してくれるかどうか」は、成果に直結するポイントです。
3. 失敗しないためのチェックリスト
最後に、RPO導入を検討する際に確認すべきチェックリストをまとめます。
- 契約前に「委託範囲」と「成果指標(KPI)」を明確にしているか
- ベンダー側の得意分野が自社の採用課題に一致しているか
- コストと成果のバランスが取れているか
- 契約期間・解約条件を事前に確認しているか
- 導入後のレポート・改善提案の仕組みがあるか
これらを押さえておけば、ベンダーとのミスマッチを防ぎ、長期的に成果を出しやすくなります。
9. RPO活用の成功事例3選|成果と背景を徹底紹介

1. 羽田空港サービス株式会社|エージェント活用で採用目標2倍を達成

羽田空港の地上業務を担う羽田空港サービス株式会社では、従来エージェントに依存していた採用活動が属人的になっていました。
RPOを導入したことで、エージェント対応を仕組み化し、採用戦略全体を最適化。結果的に、当初目標の2倍にあたる採用を実現しました。
👉 成果:採用数の大幅増加と、人事工数の削減に成功。
2. 株式会社ジュエリーバウレット|専任人事不在でも短期間で採用成功

ジュエリー販売を手がける株式会社ジュエリーバウレットでは、人事専任が不在で採用業務が滞りがちでした。
RPOにより、求人媒体の運用とスカウト代行を実施し、効率的な母集団形成を実現。結果、短期間で採用目標を達成することができました。
👉 成果:採用専任不在の状態から、スピーディに採用計画を実現。
3. 株式会社クラステクノロジー|“ひとり人事”から採用体制を仕組み化

ITソリューションを提供する株式会社クラステクノロジーでは、人事専任が1名のみで、戦略的な採用活動に着手できない課題を抱えていました。
RPO導入により、戦略立案とオペレーション支援を同時に実行。結果として、採用プロセスの仕組み化と安定した母集団形成が可能となりました。
👉 成果:属人的だった採用を脱却し、長期的に機能する体制を構築。
✅ このように、RPOは「大量採用」「専任不在」「体制構築」など異なる課題を抱える企業で成果を上げています。
重要なのは、自社の課題に合ったRPO活用法を選ぶことです。
10. まとめ|RPOを活用して採用を資産化する方法
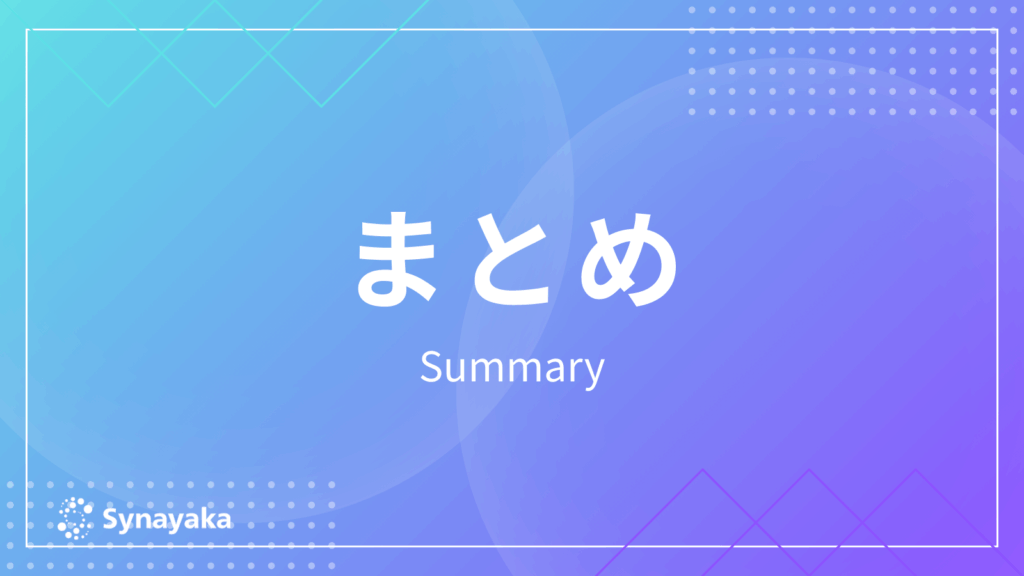
1. 本記事のまとめと要点整理
本記事では、RPOについて以下の観点から解説しました。
- RPOとは何か:採用プロセス全体を外部に委託し、成果を最大化する仕組み
- BPOとの違い:幅広い業務を対象とするBPOに対し、RPOは採用に特化
- メリットとデメリット:母集団形成や効率化で強みを発揮する一方、コストや依存のリスクもある
- 市場規模と動向:2025年には国内市場が約1,000億円規模に拡大
- サービス範囲:求人作成から内定フォローまで幅広く対応可能
- 費用相場と契約形態:月額固定・成果報酬・従量課金など多様な選択肢がある
- 活用すべき企業の特徴:大量採用・スタートアップ・人事リソース不足の企業に有効
- ベンダー選びのポイント:得意領域・実績・体制を見極めることが重要
- 成功事例:羽田空港サービス、ジュエリーバウレット、クラステクノロジーなどで成果が実証
2. RPOを導入すべき企業への提言
採用を取り巻く環境は、人口減少・求人倍率の上昇・候補者ニーズの多様化などで年々難易度が増しています。
その中で、RPOは「工数削減」だけでなく、戦略的に採用を成功に導くパートナー として機能します。
ただし、万能ではありません。
- 小規模な採用計画
- 特殊すぎる職種
- 内製化を重視する文化
といったケースでは部分委託や別の手法が適する場合もあります。
重要なのは、自社の採用課題を正しく整理し、それに合うRPOの形を選択することです。
3. SynayakaのRPO支援と無料相談

私たちSynayakaは、
- WantedlyやLinkedInなど運用型媒体の最適化
- 採用ブランディングやEVP設計支援
- AI活用によるスカウト最適化・PDCA運用
といった強みを活かし、「アルゴリズム×ブランディング×構造設計」で成果を出すRPO をご提供しています。
「RPOが自社に合うのか知りたい」「部分的に試してみたい」といった段階でも問題ありません。
まずは無料相談で、御社に合った最適なRPO活用方法をご提案いたします。
「Wantedly完全攻略」White Paper 限定配布中!
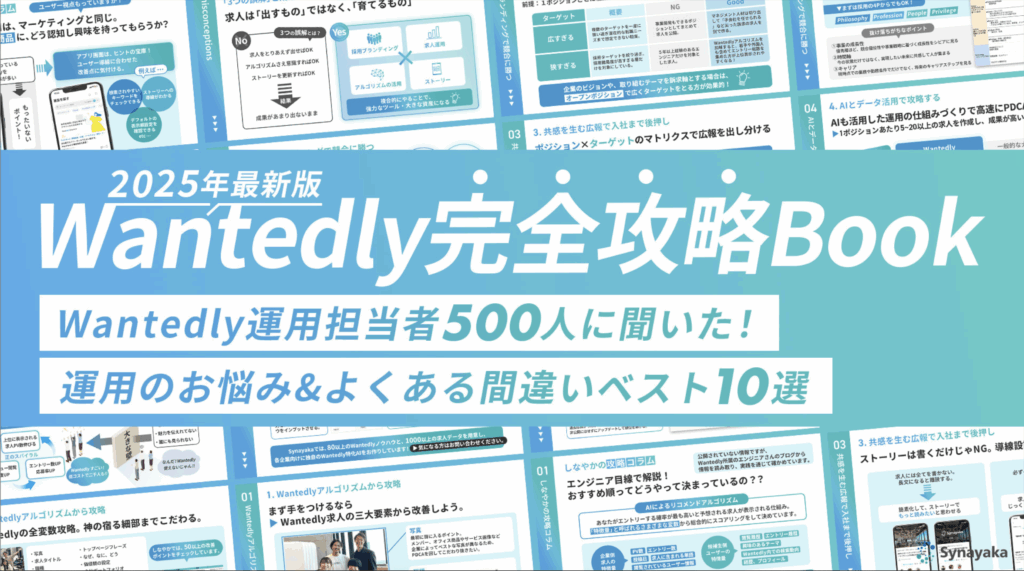
費用相場の全体像は掴めたでしょうか?
ただ、Wantedlyは「料金」だけで成果が決まるわけではありません。
実際には アルゴリズム対策・記事設計・ブランディング が成果を左右します。
こうしたノウハウを体系的にまとめたのが、弊社で配布している 「2025年版 Wantedly完全攻略Book」。
実際の成功事例や改善チェックリストも載せていますので、料金を比較した後に「何から改善すべきか?」がすぐわかります。