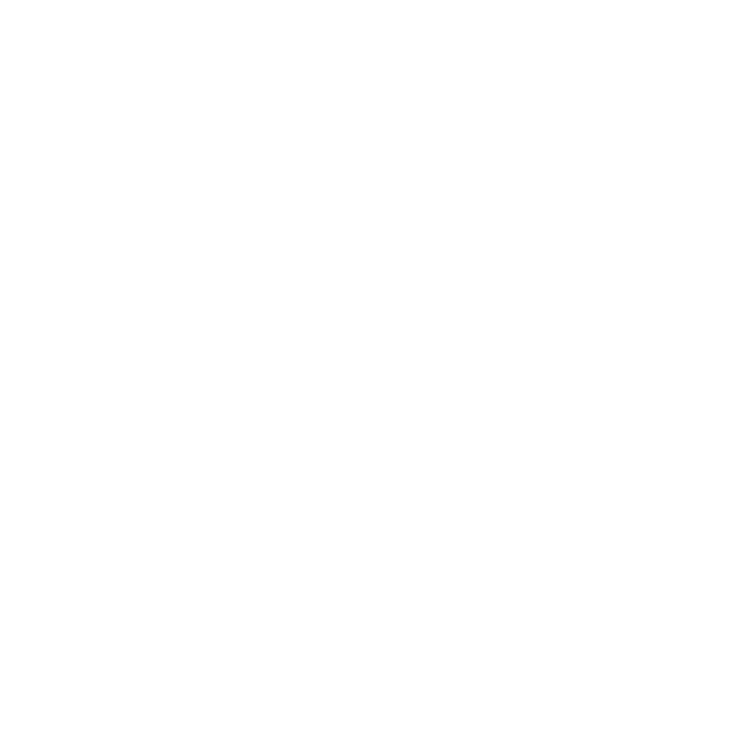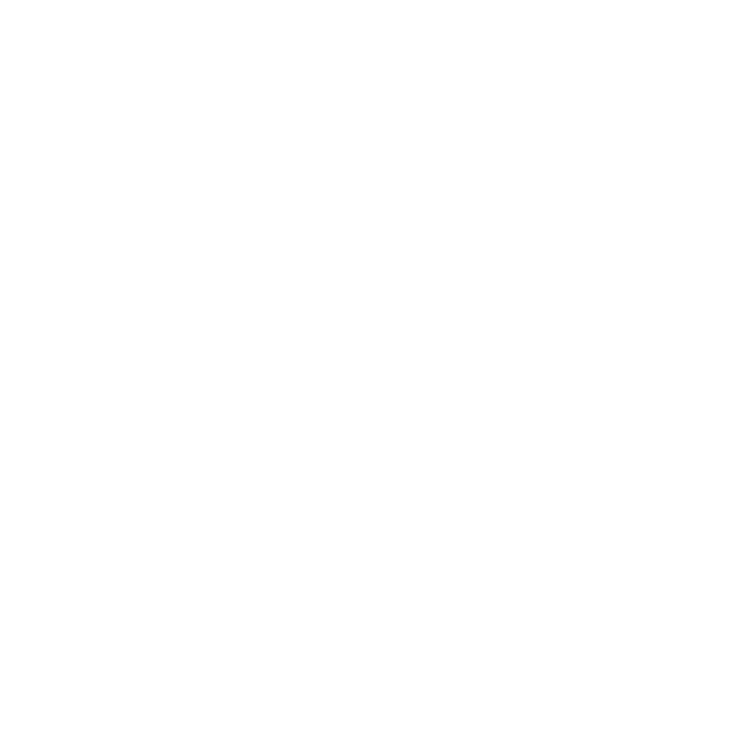システムエンジニア採用の成功法|転職理由から逆算する5つのコツ
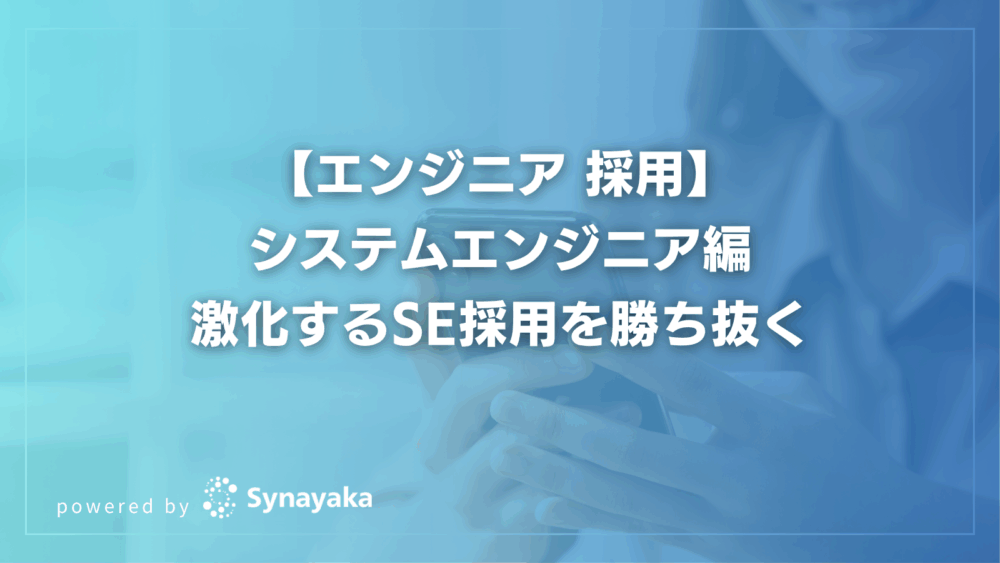
①|システムエンジニア採用市場の現状と背景
近年、システムエンジニアを含むITエンジニアの採用が、企業にとってかつてないほど難易度の高いものになっています。とくに中途採用における「システムエンジニア 採用」は、採用市場の中でも有効求人倍率が非常に高く、売り手市場が続いています。
dodaの「転職求人倍率レポート」でも、IT・通信分野は全業界の中でも常にトップクラスの倍率を誇り、企業が求めるスキルや人材像にマッチするエンジニアを確保するには、従来の手法では太刀打ちできない状況です。
有効求人倍率の推移と売り手市場の加速
2020年代に入って以降、特にコロナ禍以降のリモートワークやDX推進の流れも追い風となり、エンジニア職の求人は急増。一方で、エンジニア人材は育成に時間がかかり、即戦力層の母数は限られているため、常に需要が供給を上回る構造になっています。
この「供給不足×採用難化」の傾向は、今後も当面続くと見られています。
ITエンジニア職が特に採用難とされる理由
特にシステムエンジニアの採用が難しい背景には、以下のような要因があります。
- 即戦力として求められるスキル幅が広い
- 要件定義や顧客折衝など“ビジネス理解”も必要
- SESや受託の働き方から脱却したいニーズが増加中
企業側が求めるスキルセットと、候補者が希望する働き方・プロダクトとのギャップが大きくなりやすく、「条件を提示しても応募が来ない」状態に陥るケースも多発しています。
待ちの採用から「攻めの採用」へのシフト
これまで多くの企業が「求人広告を出して応募を待つ」スタイルに頼ってきました。しかし現在のシステムエンジニア採用において、この方法はほとんど通用しなくなっています。
求める人材に直接アプローチするダイレクトリクルーティングや、自社の魅力をしっかりと言語化・発信するブランディング型採用が求められるようになり、採用活動そのもののパラダイムシフトが起きているのです。
このように、システムエンジニア採用を成功させるためには、市場構造と時代の流れを理解した上での「採用の再設計」が必要不可欠です。
②|システムエンジニアの種類と仕事内容を理解する【修正版】
「システムエンジニア」という言葉は広く使われていますが、実際にはさまざまな職種・役割が含まれています。採用成功のためには、「どのエンジニア職を指しているのか」「どんなスキル・志向を持つ人材を求めているのか」を明確にすることが不可欠です。
本記事では、主に開発領域に携わるシステムエンジニアを中心に、その種類と役割を整理します。
アプリケーションエンジニア|業務系・Web系の違い
アプリケーションエンジニアは、ユーザーが直接利用するシステムやサービスの開発を担当します。大きくは以下のように分類できます。
- 業務系エンジニア:金融、製造、物流など、特定業種の業務フローを支えるシステム開発が中心。安定性・堅牢性が重視されます。
- Web系エンジニア:自社プロダクトやWebサービスの開発を担い、UI/UX・ユーザー視点を重視。アジャイル開発やスピード感のある改善サイクルに慣れている人材が多いです。
システムエンジニア(SE)|要件定義から設計を担う上流工程
システムエンジニアは、顧客や社内の要望を整理し、システムとして設計・実装できる形に落とし込む役割を担います。いわゆる「要件定義〜基本設計〜詳細設計」といった上流工程に強く、クライアントとのコミュニケーション能力や業務理解力も求められます。
企業によってはSEが設計から開発、保守まで一気通貫で行うこともあり、汎用性の高い技術者として重宝されるポジションです。
補足:インフラや組み込みなど、周辺技術領域の分類
システムエンジニアとは領域が異なりますが、ITエンジニアの中には以下のような技術職も存在します。
- インフラエンジニア/ネットワークエンジニア:システムを支える基盤の構築・運用を担当
- 組み込みエンジニア:IoTやハードウェアに密接に関わる領域でC言語などを使用
- SREやDevOps系の技術者:開発と運用の橋渡しを担い、信頼性や運用自動化に寄与
これらは採用戦略上は明確に分けて設計すべき領域であり、本記事では主にアプリ/業務系の開発職にフォーカスを当てています。
以上のように、システムエンジニアと一口に言っても、その定義や対象職種は広いため、採用ターゲットに合わせた精緻な職種設計が重要となります。
③|転職理由から逆算するシステムエンジニア採用のコツ
システムエンジニア採用で最も重要な視点の一つが、「なぜその人は転職を考えているのか?」という転職理由の深掘りです。
dodaが発表している転職理由の調査によると、ITエンジニアの転職には明確な傾向があります。これらの背景を理解し、それぞれに刺さる“訴求メッセージ”を設計することで、求人の反応率は大きく変わります。
上位に多い転職理由TOP3とその背景
ITエンジニア全体の転職理由(doda調査)で上位に挙がるのは、以下の3つです。
- 他にやりたい仕事がある(キャリアの方向転換)
- 専門知識・技術を習得したい(スキルアップ志向)
- 給与に不満がある(待遇改善)
これらは「成長機会」と「報酬」に直結しており、システムエンジニアの場合は特に技術的チャレンジや裁量のある開発環境を求める声が多く見られます。
転職理由別|刺さる訴求ポイントの具体例
以下は、代表的な転職理由とその対策として有効な訴求軸の整理です。
| 転職理由 | 有効な訴求ポイント例 |
|---|---|
| 他にやりたい仕事がある | 「新規プロダクト立ち上げ」「上流工程へのチャレンジ」 |
| 専門知識を習得したい | 「モダン技術スタック(例:Go, React, AWS)」 「勉強会や技術研修の支援制度」 |
| 給与に不満がある | 「年収レンジの明示」「インセンティブ制度の設計」 |
| 市場価値を上げたい | 「フルサイクル開発」「顧客との折衝機会」「自社プロダクト」 |
| 幅広く経験を積みたい | 「複数プロダクトの運営」「スクラム型チームでの横断業務」 |
特にSEの場合、「単なる作業者」ではなく“ビジネスと技術の橋渡しができる人材”として成長したいという声が多く、ポジションの将来像を丁寧に描くことで応募率が高まります。
SEが「応募したくなる求人」に共通する特徴
転職市場の声を整理すると、共通して好まれる求人の特徴には以下の傾向があります。
- 開発における裁量と責任が明確に示されている
- 評価基準・キャリアパスがオープンにされている
- CTOやリーダーの思想が発信されている
- 技術選定・アーキテクチャの方針が共有されている
- エンジニアの働き方(フルリモート・副業可など)に柔軟性がある
こうした要素を盛り込むことで、候補者の「転職理由」に対応する形で共感と行動(応募)を促す構造が作れます。
④|システムエンジニアが惹かれる魅力設計と採用ブランディング
求人を見たときに「ここ、気になるかも」と思わせる第一歩は、“何を求める人に、どんな魅力を、どんな言葉で届けるか”を徹底的に設計することです。特にシステムエンジニアのような専門職では、技術やプロダクトに対するこだわりや志向性に合わせた訴求が重要です。
プロダクト志向・技術志向に刺さる訴求とは?
開発や設計にこだわりを持つシステムエンジニアには、「その会社で何を設計できるか」「どんな体験を提供できるか」が刺さります。
たとえば、以下のようなポイントが響きやすい訴求軸です
- 技術的チャレンジができる環境か(例:マイクロサービス、DDD、技術選定の自由度)
- プロダクトへのオーナーシップがあるか(上流から下流まで携われる/顧客に近い開発)
- チームの技術レベルや文化が合っているか(エンジニア主導の文化、リファクタ文化)
つまり、単に「働きやすさ」ではなく、“技術者として誇れる環境かどうか”を軸にした言語化が必要です。
社内体制やカルチャーの“伝え方”で差がつく
SE採用で成果が出る企業は、単に制度を並べるのではなく、「なぜその制度があるのか」「どんな背景でその文化が生まれたか」をストーリーで語っています。
特に響くポイントは以下のようなものです
- なぜ自社がその技術スタックを選んでいるのか
- エンジニアが意思決定に参加できる組織か
- 上長やCTOがどういう思想で育成しているか
これらを、求人ページや会社紹介の中で一貫した言葉で語ること=採用ブランディングです。共感してもらえる“物語”があるかどうかで、応募者の印象は大きく変わります。
競合と差別化するEVP(価値提案)の言語化方法
求人が溢れる中で、「どこも似たようなことを言っている」と思われた時点でスルーされてしまいます。だからこそ、自社にしかない魅力=EVP(Employee Value Proposition)の整理が必要です。
EVPは、次の3Cで考えると整理しやすくなります。
| 項目 | 観点 |
|---|---|
| Company(自社) | 他社にはない制度・文化・こだわり |
| Competitor(競合) | 他社が訴求していない切り口・技術領域 |
| Candidate(候補者) | 転職時に候補者が求めていること |
この3つが交わる部分を、求人やストーリーでブレずに言語化することで、応募率や面談率が格段に向上します。
⑤|Synayakaの強みと支援実績|エンジニア採用の成果を最大化
システムエンジニア採用を成功させるためには、「媒体に求人を出す」だけでは不十分です。求める人材に対して、何をどのように届けるかを設計する“採用ブランディング力”が求められます。
Synayakaは、開発・システムエンジニアの採用に特化した支援を行っており、特に中小・スタートアップ企業における“自社らしい魅力”の言語化と設計を得意としています。
元エンジニアが設計する“共感型”採用戦略
Synayaka代表は元ITエンジニアというバックグラウンドを持ち、職種や技術領域ごとの志向性や転職動機に対する理解が深いのが特徴です。
そのため、求人の言語設計やペルソナ設計、Wantedlyなどでの運用においても、「この技術者にはこの表現が刺さる」といった細かなチューニングが可能になります。
また、CTOや開発責任者と技術的な視点で会話ができるため、単なる採用代行ではなく、“事業と技術に沿った採用設計”を共に作るパートナーとして機能します。
採用ブランディング×ペルソナ設計で成果を出す仕組み
Synayakaの支援では、まず以下のような「構造設計」から着手します。
- 誰を採用したいか(ペルソナ)
- その人は何を求めているか(転職動機・志向性)
- 自社にある“響く魅力”は何か(EVP)
- どの媒体・コンテンツでどう届けるか(導線設計)
この一貫した構造をもとに、求人タイトル・文章・ストーリー・スカウトまでを“候補者視点”で整えることで、「共感→応募→面談」の反応率を高めていきます。
特にWantedlyを活用した採用では、280社以上の実績を活かしたノウハウも蓄積しており、運用改善から数値分析、改善サイクルの構築まで一気通貫で支援しています。
中小・スタートアップ企業の成功事例と支援実績
以下のような企業で成果を出しています
- スタートアップ企業A:Wantedly経由で月4件の応募→半年でエンジニア3名採用に成功
- SaaS企業B:EVPとスカウト改善により、クリック率2.4倍・返信率1.8倍に向上
- 地方企業C:UIターン希望エンジニア向けの訴求設計で月1名ペースの採用に成功
これらの成功事例に共通しているのは、「誰に向けて・どんな魅力を・どう届けるか」を徹底的に言語化・設計したことです。
システムエンジニア採用においては、“採用設計とブランディング”こそが、限られたリソースで最大の成果を出す鍵となります。
Synayakaは、技術理解×設計力×運用ノウハウを武器に、あなたの会社の“仲間集め”を支援します。
まとめ|システムエンジニア採用は「誰に何をどう伝えるか」で決まる
本記事では、「システムエンジニア 採用」をテーマに、市場動向から職種理解、転職理由別の訴求、そしてブランディング戦略まで一気通貫で解説してきました。
📌この記事でお伝えした重要ポイント
- 採用市場は売り手化が進み、特にシステムエンジニアは超争奪戦
- SEの役割や分類を理解し、自社に必要な人材を明確化する
- 転職理由を理解すれば、求人に“刺さる言葉”が設計できる
- 技術志向やプロダクト志向に合わせた魅力設計が鍵
- 採用はブランディングと設計。Synayakaがその設計を支援可能
求人媒体やスカウト文面、面談での会話――
どれか一つが“響かない”だけで、優秀な候補者との出会いはすれ違ってしまいます。
だからこそ、採用は「誰に・何を・どう伝えるか」の設計がすべてです。
もし、今の採用がうまくいっていない、応募が伸びないと感じているなら、一度その“伝え方”を見直してみてください。
Synayakaでは、システムエンジニア採用に強い設計・運用支援を行っています。
採用ブランディング/ペルソナ設計/求人改善/スカウト運用など、お困りの方はぜひ一度ご相談ください。